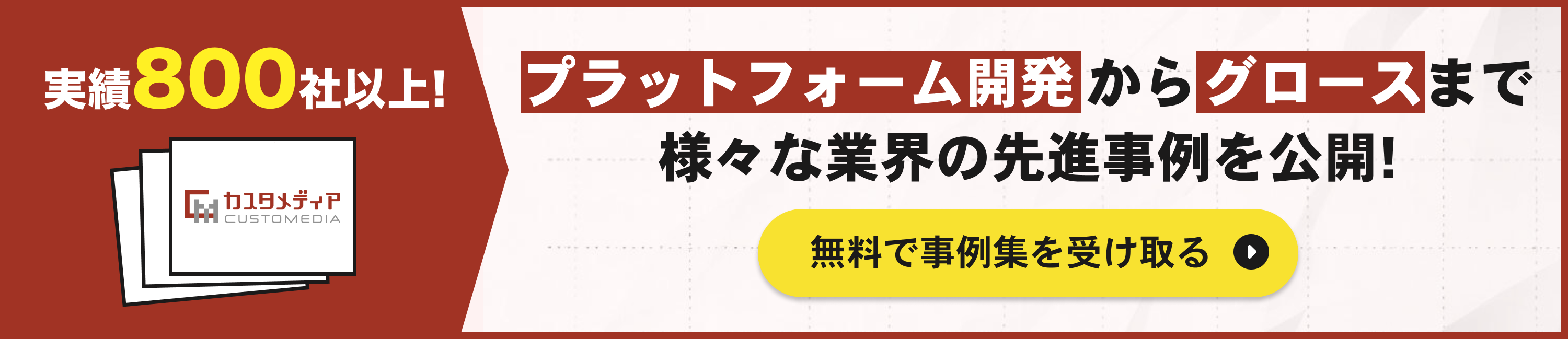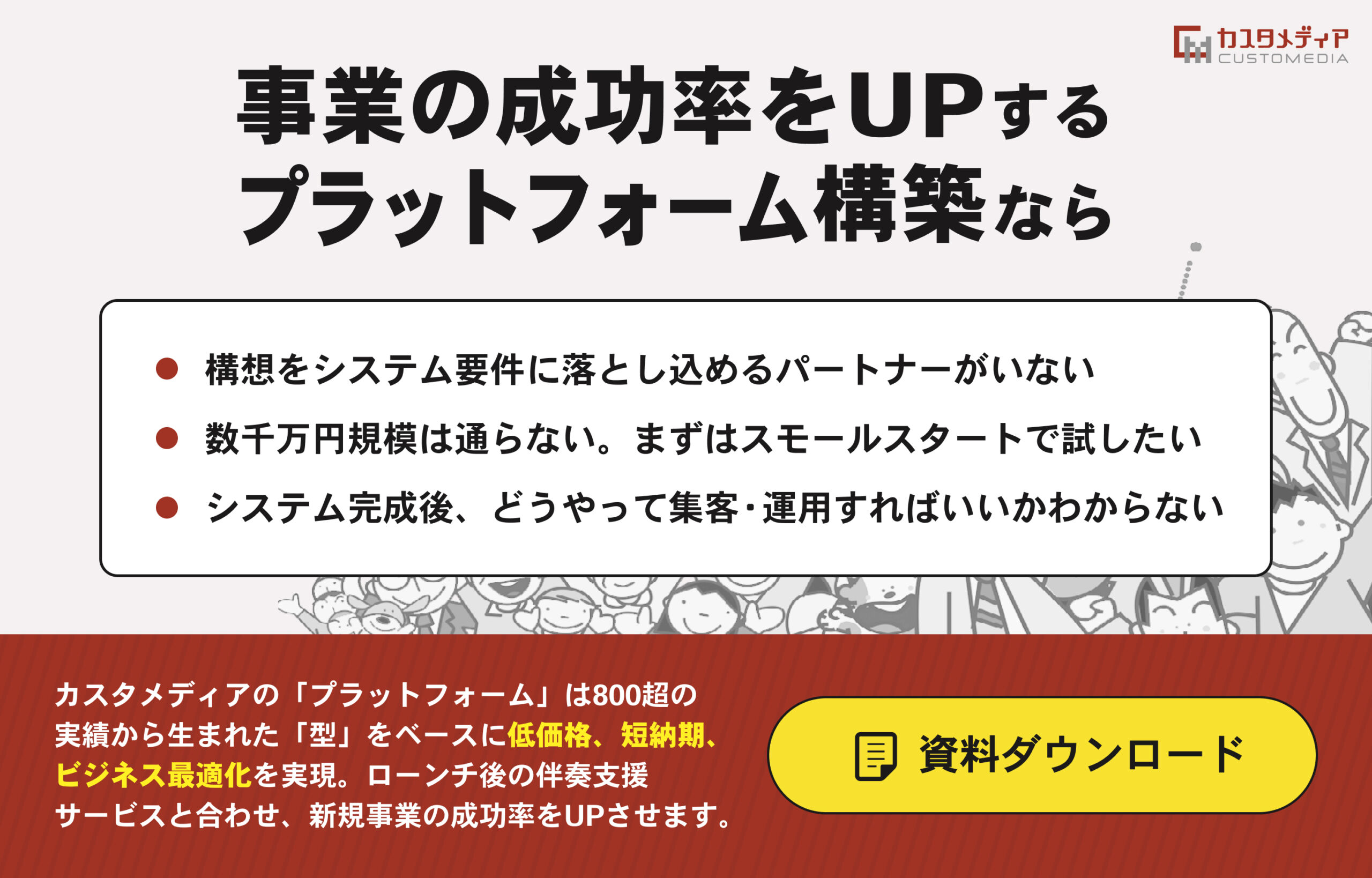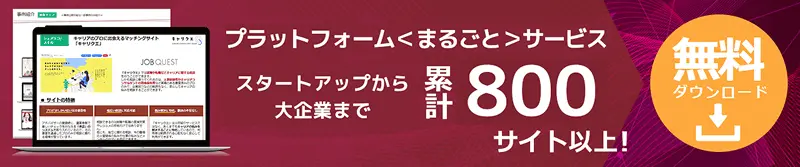マーケティングBLOG
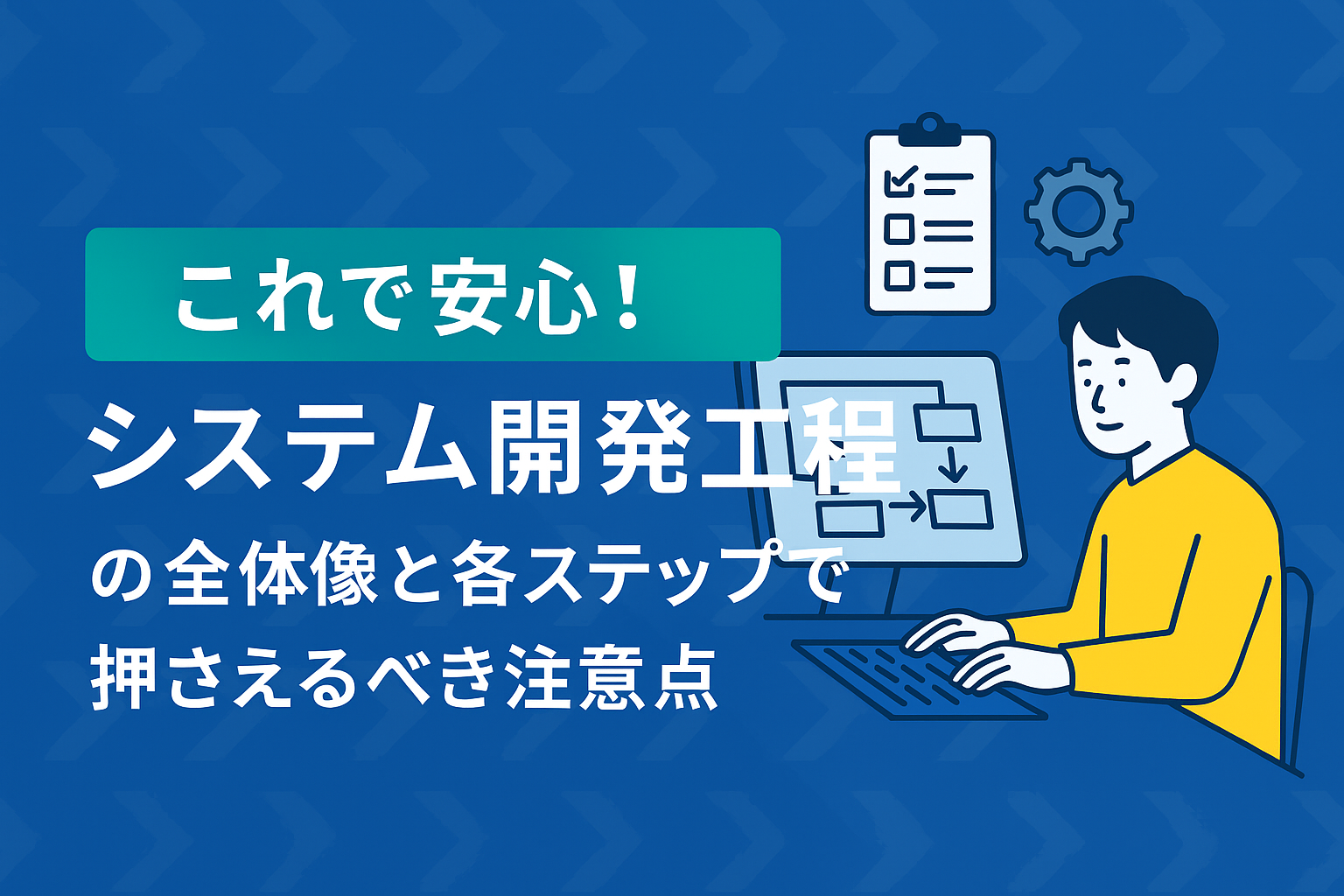
これで安心!システム開発工程の全体像と各ステップで押さえるべき注意点
導入実績800サイト以上!!
「カスタメディア」の事例ダウンロードは
こちら
システム開発工程は、企業が新しいシステムを導入するときに欠かせない手順の集合体です。初めて開発に関わる担当者や、外注を検討している方にとって、この流れを理解しているかどうかは成功率を大きく左右します。
工程は大きく「要件定義 → 設計 → 実装 → テスト → 運用」という順序で進みますが、どの段階も単なる通過点ではなく、次の工程に確実につなげるための土台です。もしどこかが疎かになれば、後から手戻りやコスト増大につながる危険があります。
この記事では、各工程の目的や注意点を詳しく解説し、初心者でも理解できるように整理しました。
目次
システム開発工程とは何か

システム開発工程とは、アプリや業務システムを計画的に作り上げるためのプロセスです。家を建てる場合に「設計図なしで工事を始めると失敗する」のと同じで、ソフトウェア開発も工程を踏むことが重要です。
一般的には以下の流れで進行します。
- 要件定義:どんな機能が必要かを決める
- 設計:仕組みや構造を形にする(基本設計/詳細設計)
- 実装:実際にプログラミングを行う
- テスト:不具合を修正し、動作確認を行う
- 運用:完成後に利用しながら改善する
この流れを知っているだけでも、外注先と話すときに会話がスムーズになり、見積もりや契約内容を理解しやすくなります。特に外部ベンダーに委託する場合、工程ごとの成果物(要件定義書、設計書、試験成績書、運用手順書)が検収の基準になるため、早い段階から“何をもって完了とするか”を合意しておくことが肝心です。
システム開発の基本概念
システム開発の根幹は 要求分析・設計・プログラミング・テスト・運用 に分けられます。
- 要求分析:ビジネスの目的を明確にし、ユーザーが求める機能を洗い出す。現場ヒアリング、業務フロー図、ユースケース、ペルソナなどを用いる。
- 設計:要件を基にシステムの構成を描く。アーキテクチャ、データモデル、画面・API、外部連携、セキュリティや性能方針を決める。
- プログラミング(実装):設計図をコードに変換して形にする。コーディング規約、コードレビュー、CI/CD で品質と速度を両立。
- テスト:動作が正しいか検証し、不具合を修正する。単体・結合・システム・運用テストの多層で品質を担保。
- 運用:実際に利用し、改善や保守を継続する。監視、バックアップ、脆弱性対応、ログ分析で“使われ続ける”状態を維持する。
この概念を理解しておくと、全体像をつかみやすく、開発の進行が見えやすくなります。初心者は「各工程での入力(インプット)と出力(アウトプット)」を意識すると、迷いにくくなります。
システム開発の重要性
システム開発は、企業にとって単なるIT投資ではありません。効率化やデータ活用を通じて競争力を高める戦略的な取り組みです。
- 業務効率の向上:手作業を自動化することで社員の負担を軽減。入力ミスの削減、処理時間短縮が直接コストに効きます。
- 顧客満足度の向上:顧客に使いやすいシステムを提供できる。応答速度、UI/UX、サポートの迅速さは評価に直結。
- 競争力の強化:最新技術(クラウド、API連携、データ可視化)を取り入れることで市場で優位に立てる。
外注する場合も工程を理解していれば、「費用が高いのか安いのか」「納期が現実的か」などを正しく判断できます。さらに、非機能要件(性能・可用性・セキュリティ・運用)を数値で定義し、契約に組み込むことで、後からの解釈の揺れを抑えられます。
システム開発の工程一覧
典型的な流れは次の通りです。
- 要件定義:システムに必要な機能や条件を整理
- 設計:基本設計と詳細設計に分け、構造を決定
- 実装:プログラムを書き、機能を実現
- テスト:バグを洗い出し、安定性を確認
- 運用:システムを使いながら改善・保守
それぞれの工程は独立しているようで、すべてが連鎖しています。どこかの精度が低いと、次工程に負債が伝播し、最後に“大きな修正”として戻ってきます。節目ごとの合意(ゲート)を明確にして、迷いを早期に解消しましょう。
プロジェクト計画

プロジェクト計画は開発のスタート地点です。ここで「何を達成するか」「いつまでに完成させるか」「どの程度の予算をかけるか」を決めます。
- 目的とゴールを明確にする:例)手作業を30%削減、応答2秒以内、稼働率99.9%
- スケジュールを現実的に組む:マイルストーンとクリティカルパスを可視化
- 必要な人材やスキルを洗い出す:内製/外注の分担、意思決定フローも明示
- 想定されるリスクに備える:法令・セキュリティ・データ移行・外部依存・人員離脱
計画があいまいだと、途中で方向性がぶれてトラブルの原因になります。決定事項の記録テンプレート(目的/選択肢/決定理由/影響範囲)を用意しておくと、後から見返したときに納得感が保てます。
要件定義

要件定義は「プロジェクト成功の7割を決める」ともいわれる重要な工程です。ここで顧客や利用者のニーズを正しく理解し、文書にまとめます。
- ヒアリング:業務フローや課題を整理。現場の“つまずき”を具体例で集める
- 機能要件:システムに必要な機能を定義。ユースケース、受け入れ基準をセットで記述
- 非機能要件:処理速度やセキュリティ、可用性、バックアップ、ログ、監視などを数値化
- 優先順位付け:MUST/SHOULD/COULD で段階化し、スコープを管理
外注の場合は「言った・言わない」のトラブルを避けるため、必ず契約書や要件定義書として残すことが大切です。変更管理(いつ、誰が、何を変更し、影響はどこか)も同時に合意しておくと、後半が安定します。
基本設計
基本設計は、要件定義を「設計図」に落とし込む段階です。
- システム全体の構造:レイヤー構成、クラウド/オンプレ、冗長化戦略
- データベース設計:主要エンティティ、リレーション、整合性ルール
- 画面構成と操作フロー:主要画面のワイヤーフレーム、一覧・検索・フィルタの方針
- 外部システムとの連携方針:API 仕様、認証・認可、スループット想定
基本設計が甘いと後の工程で混乱が生じます。経験豊富なエンジニアをアサインし、構成図・ER 図・API 一覧・画面一覧を整えることで、ステークホルダー間のイメージが揃います。セキュリティと性能(キャッシュ、非同期処理、スケーリング)もこの段階で方針化しておきましょう。
詳細設計
詳細設計は、基本設計をさらに具体化する工程です。プログラマーが迷わず実装できるように、仕様を細かく記述します。
- 入力チェックの方法:必須、形式、桁数、文字種、メッセージ定義
- エラー発生時の処理:再試行、ロールバック、ユーザー通知の流れ
- テーブルのカラム定義:型、制約、インデックス、パーティショニング
- モジュール間のインターフェース仕様:I/F 契約、例外、タイムアウト、再送戦略
詳細設計がしっかりしていれば、実装時に余計な議論が発生せず、スムーズに開発を進められます。テスト観点を設計書に同居させると、後工程の準備も前倒しできます。
実装

実装工程ではプログラマーが実際にコードを書きます。選ぶプログラミング言語やフレームワークは、システムの要件や企業のスキルセットによって異なります。
- コーディング規約を守る:命名・フォーマット・例外処理の統一
- 小さな単位で開発・確認を繰り返す:プルリクエストの粒度を適切に
- コードレビューを行い品質を担保する:観点チェックリストで属人化を防ぐ
- 自動テストや CI/CD を活用する:ビルド・テスト・静的解析・デプロイの自動化
実装はプロジェクトの中で最も工数がかかる工程ですが、効率化ツールを活用することでスピードと品質を両立できます。依存ライブラリの管理(SBOM)や脆弱性スキャンも忘れずに。
単体テスト
単体テストは、作ったモジュールが正しく動くかを確認する工程です。
- 正常系テスト:想定通りに動作するか
- 異常系テスト:入力エラーや例外処理が正しく働くか
- 自動化テスト:繰り返しの確認を効率化(CI で常時実行)
単体テストを怠ると、後の工程で大きなバグが発覚し修正コストが膨らみます。境界値テストや副作用の有無(状態が漏れないか)を重視しましょう。
結合テスト
結合テストでは、複数のモジュールを組み合わせて全体が正しく動くか確認します。データの受け渡しや処理フローに問題がないかを重点的に検証します。
ここで不具合を見逃すと、システムテストや運用段階で重大トラブルにつながるため、綿密な計画が求められます。外部 API の遅延・障害、タイムアウト、再試行、排他制御など異常系シナリオも必ず用意し、ログ/トレース ID で原因追跡しやすくしておきます。
システムテスト

システムテストは、完成したシステム全体が要件を満たしているかを確認する重要な工程です。
- 機能テスト:ユースケースどおりの結果が得られるか。権限差も確認
- 回帰テスト:修正や追加実装で既存機能が壊れていないか
- 性能・負荷テスト:応答時間、スループット、CPU/メモリ、DB I/O を計測
- 耐障害テスト:フェールオーバー、ネットワーク断、外部サービスのタイムアウト
- セキュリティテスト:入力バリデーション、認可、機微情報のマスキング、依存の脆弱性
- アクセシビリティ・多端末:キーボード操作、コントラスト、主要ブラウザ/OS
システム全体を網羅的に確認することで、ユーザーに安心して使ってもらえる品質を確保します。SLO との乖離があれば、原因切り分けと再テスト計画までをセットで提示すると判断が早まります。
運用テスト
運用テストは、本番環境を想定したシミュレーションです。実際の利用シーンを再現し、安定性や操作性を確認します。バックアップや障害対応手順のテストもここで行います。
- 運用手順の検証:日次/週次作業、夜間バッチ、月末処理を手順書どおりに実演
- 監視とアラート:監視項目・閾値・通知先・当番体制を調整
- 権限と監査:ロール定義、申請〜付与〜棚卸し、退職時の剥奪手順
- バックアップ/リストア:保持期間、実リストアの所要時間(RPO/RTO の達成確認)
- 問い合わせ・障害対応:一次切り分け、エスカレーション、影響範囲の算定、掲示テンプレート
運用テストが不十分だと、リリース後に想定外のトラブルが起きやすくなります。ロールバック演習を一度は行い、「戻せる前提」を作るのが安心への近道です。
リリース
リリースは、開発したシステムを正式に公開する段階です。ユーザーに利用してもらい、フィードバックを得ることで改善の方向性が見えてきます。
- ベータ版で一部ユーザーに先行提供:影響を限定しつつ学びを得る
- 段階的リリース:カナリア配信や機能フラグで安全性を高める
- ドキュメントやサポート体制の整備:変更点、既知の制限、連絡先、FAQ
リリースはゴールではなく、新たなスタートでもあります。作業ログの記録と強化監視期間を設け、初期の不具合を素早く検知・是正しましょう。
保守とメンテナンス
システムはリリースして終わりではありません。むしろ利用開始後が本番です。
- バグ修正やセキュリティ対応(是正・適応保守)
- 定期的なアップデートと技術的負債の解消(予防保守)
- 機能改善によるユーザー体験向上(改良保守)
継続的な保守が、システムを長く安定して利用するための鍵となります。SLA/SLO/SLI を運用し、エラー予算の考え方で「安定化か新機能か」の舵取りをするのも効果的です。
システム開発の手法
開発の進め方にはいくつかの手法があります。代表的なのが ウォーターフォールモデル と アジャイル開発、そして スパイラル型開発 です。
- ウォーターフォール:計画通りに順番に進める方法。変更に弱いが大規模案件・監査要件に適する
- アジャイル:短い期間で小さく作り、改善を繰り返す方法。柔軟性が高く探索型の開発に強い
- スパイラル:リスクを抑えつつ試作を重ねる方法。不確実性の高い大規模案件に有効
プロジェクトの性質に応じて手法を選択することが重要です。実務では、領域ごとにハイブリッド(例:基幹はウォーターフォール、UI はアジャイル)にするのが現実的です。
システム開発工程の管理

工程管理は「進捗の見える化」と「合意形成」がポイントです。タスク管理ツールを使い、進捗を共有し、定例ミーティングで認識を合わせます。
また、工程ごとにレビューを行い、問題を早期に発見・修正することが成功への近道です。議事録・決定事項・変更履歴を一元管理し、誰が見ても経緯が辿れる状態を保ちましょう。欠陥密度、テストカバレッジ、リードタイム、MTTR などの指標を運用すると、改善の優先度が決めやすくなります。
品質向上の方法
品質を高めるには、工程ごとに工夫が必要です。
- 初期段階で非機能要件を明確にする(数値で定義し、設計へ反映)
- コードレビューを徹底する(観点チェックリストで属人化を回避)
- 自動テストや CI/CD を導入する(小さく早く届けて不具合を局所化)
- プロトタイプでユーザー体験を早期に検証する(早い実見は手戻りを減らす)
「品質を作り込む仕組み」を整えることで、全体の信頼性が高まります。アクセシビリティとセキュリティは“最初から要件”として扱うのがコツです。
プロジェクト管理の効率化
効率化にはツールとルールが欠かせません。
- タスク管理ツールで進捗を見える化:担当・期限・完了条件を明記
- 優先順位をつけて作業を整理:MUST/SHOULD/COULD で段階化
- 定例レビューで軌道修正:短時間・高頻度でズレを早期に発見
- 承認フローを簡潔にする:代替承認者を定義し、停滞を防止
効率的な管理は、納期と品質を両立させるための基盤です。テンプレート(要件・設計・テスト・障害報告)を整えると、教育コストも下がります。
コスト削減のメリット
システム開発におけるコスト削減は「安くする」ではなく「無駄をなくす」ことです。
- SaaS や既存サービスを活用して“作らない選択”
- 再利用できるモジュールやコードを蓄積(共通部品・UI コンポーネント)
- 自動テストで検証コストを下げる(回帰に強いテスト資産を育てる)
これらを積み重ねることで、トータルコストを抑えつつ高品質な開発が可能になります。監視・ログ基盤の標準化は、障害対応の時間とストレスを大きく減らします。
システム開発で知っておきたい略語
略語を理解しておくことで、資料や会話がスムーズになります。最初に共通用語集を作ってチームで共有しておくと、意思疎通の速度と正確性が上がります。
SP(システム企画)
システム企画では、まず「どんな課題を解決したいか」を定義します。現状の業務フローやシステムの課題を分析し、改善すべきポイントを特定します。ここでの分析が甘いと、後の要件定義がずれやすくなります。期待効果(KPI)を数値で置くと、投資判断と優先順位付けがしやすくなります。
SA(要求分析)
要求分析では、ユーザーや関係者から情報を収集し、具体的なニーズを洗い出します。インタビューやアンケート、ワークショップを活用することが多いです。収集した要求は、ユーザーストーリーやユースケースとして可視化し、合意形成を進めます。
RD(要件定義)
要件定義では、収集した要求を機能要件・非機能要件に分類します。ここで曖昧な部分を残すと後の工程で大きな問題になります。契約や検収の基準となる重要なドキュメントです。受け入れ基準を明記し、テストと検収に直結させるとスムーズです。
BD(基本設計)
基本設計では、システム全体の構成を決めます。画面、データベース、外部連携、セキュリティなど、骨組みを固める工程です。設計が甘いと、後の実装やテストで不具合が連発します。構成図・ER 図・API 一覧など、目で見て理解できる資料が効果的です。
UI(ユーザーインターフェース設計)
UI 設計はユーザーが直接触れる部分です。操作のしやすさやデザイン性が利用者の満足度を左右します。フォームの入力負担、エラーメッセージの分かりやすさ、色覚多様性への配慮、キーボード操作などを初期から検討することが重要です。プロトタイプで早期に体験を確かめましょう。
DD(詳細設計)
詳細設計は、基本設計をさらに細分化したものです。データの入出力条件やエラー処理の流れ、画面ごとの細かい仕様を定義します。プログラマーにとっての道しるべとなります。テスト観点(境界値、異常系、パフォーマンス)もここで一緒に明確化すると、後工程が楽になります。
PG(プログラミング)
プログラミングは、詳細設計をもとにコードを書き、システムを具体化する工程です。命名規則やコードレビューを徹底し、品質を確保します。CI/CD を導入することで自動的にビルドやテストを行えるため、効率的です。小さく作って早くフィードバックを得るのが成功の近道です。
UT(単体テスト)
単体テストでは、各モジュールが仕様通り動くか確認します。バグを早期に発見することで、後工程の修正コストを大幅に削減できます。自動化して回帰テストに強い基盤を作りましょう。
IT(結合テスト)
結合テストでは、複数のモジュールを連携させて正しく動作するかを確認します。外部システムとの接続やデータの整合性も検証対象です。非同期処理やリトライ、タイムアウトなど実運用で起こりうる揺らぎを意識して試験します。
ST(システムテスト)
システムテストは、要件定義で定めた条件を満たしているかを総合的に評価します。単なる「一通り触ってみる確認」ではなく、要件(機能/非機能)に対する証跡を収集する公式な検証です。ここでは次の観点を計画的に実施します。
- 機能テスト/回帰テスト
- 性能・負荷テスト/耐障害テスト
- セキュリティテスト/アクセシビリティ・多端末対応
結果は不具合の再現手順・原因推定・修正方針・再発防止策と合わせて記録し、リリース可否の判断材料にします。SLO からの乖離があれば原因を切り分け、再テスト計画を提示します。
OT(運用テスト)
運用テストは、本番運用を“予行演習”する工程です。運用手順・監視・権限・バックアップ・問い合わせ対応が、現場で本当に回るかを確認します。ロールバック演習を最低一度は実施し、戻せる前提を作ると初動の品質が向上します。
まとめ

システム開発は、要件定義で狙いを合わせ、設計で形にし、実装とテストで確かめ、運用で磨き続けるプロセスです。完璧を一度で求めるよりも、小さく作って早く学ぶ姿勢が結局は最短ルートになります。工程の意図をチームで共有し、節目ごとの合意・記録・可視化を徹底すれば、品質・納期・コストのバランスが整い、“使われ続けるシステム”に育っていきます。公開後もユーザーの声と運用データを手がかりに改善を続け、価値を積み上げていきましょう。