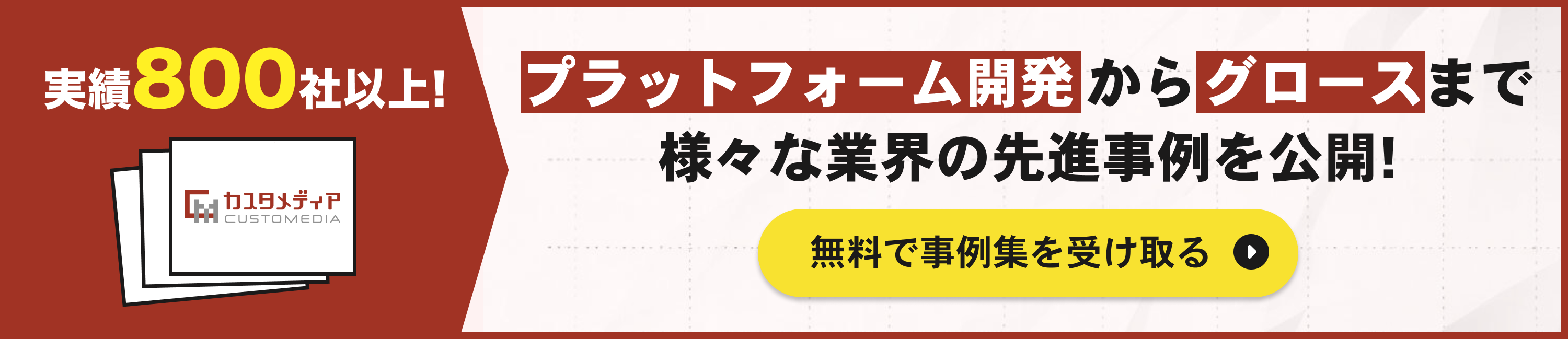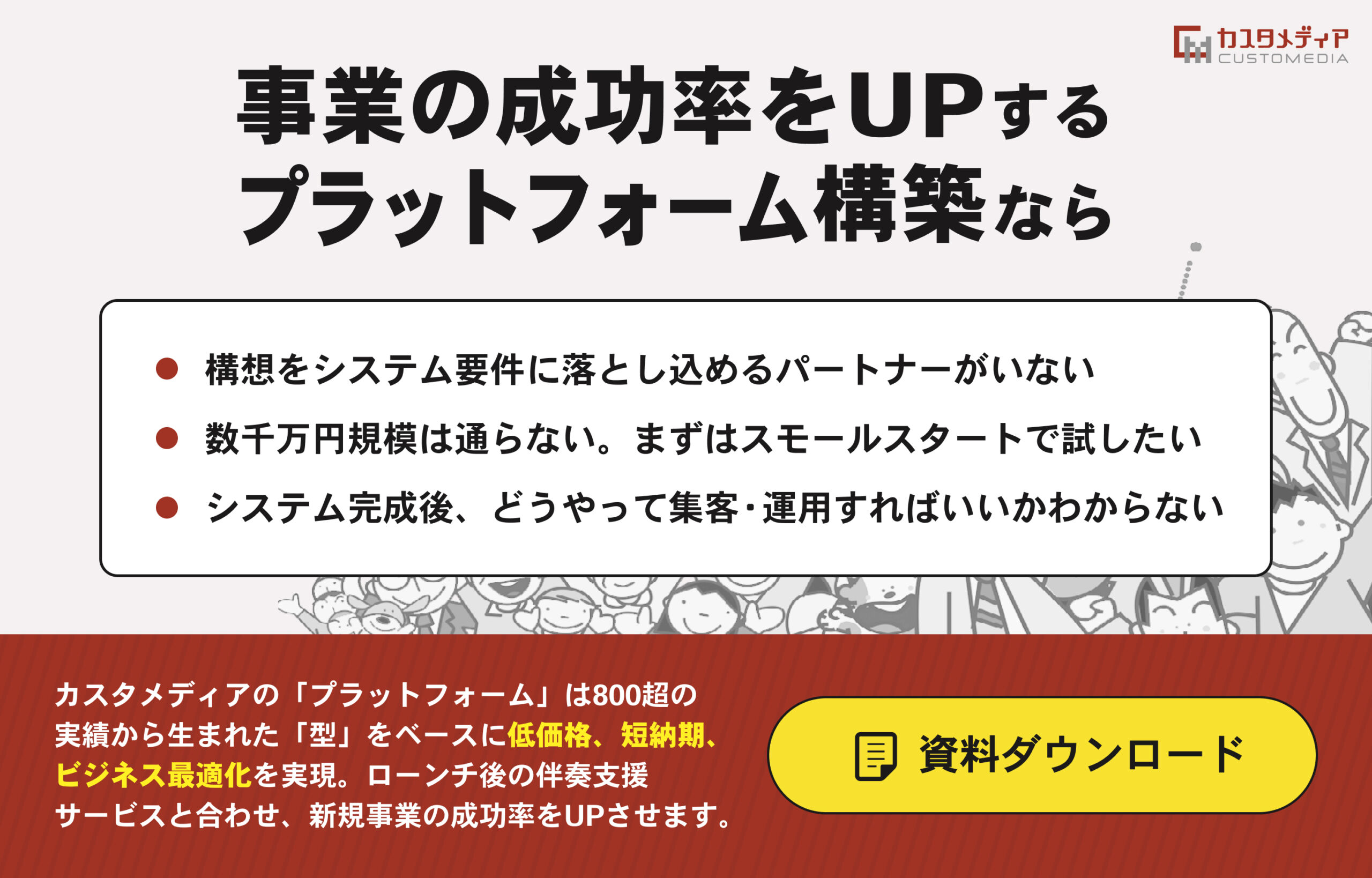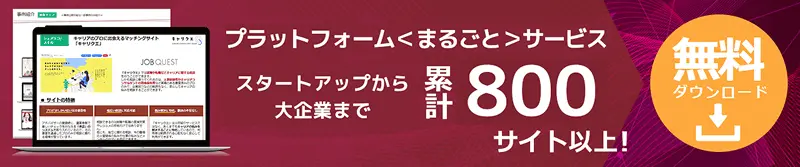マーケティングBLOG

大阪でシステム開発を依頼する前に必読!DXを成功させるパートナー選定術
導入実績800サイト以上!!
「カスタメディア」の事例ダウンロードは
こちら
大阪は、西日本を代表する経済の中心地であり、数多くの企業が拠点を構えています。この活気あるビジネス環境において、企業の競争力を維持・強化し、持続的な成長を遂げるためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が不可欠です。その中核を担うのが、業務プロセスの最適化や新たなビジネス価値の創出を実現するシステム開発です。
特に、変化の激しい現代市場においては、クラウドサービスやAI(人工知能)、IoTといった先端技術を活用したシステムへの需要が急速に高まっています。これらの技術を導入することで、データに基づいた迅速な意思決定、生産性の飛躍的な向上、そして顧客満足度の高いサービスの提供が可能となります。
しかし、「システム開発を検討しているが、何から始めれば良いかわからない」「大阪には多くの開発会社があり、どの会社を選べば良いか判断できない」といった悩みを抱える企業担当者様も少なくないでしょう。
本記事では、大阪でシステム開発を検討されている企業様に向けて、システム開発の現状と重要性、開発会社の種類と選び方のポイント、プロジェクトを成功に導くための具体的な手法、そして費用相場やコストを抑える方法まで、網羅的に解説します。信頼できるパートナーを見つけ、ビジネスを次のステージへと導くための一助となれば幸いです。
目次
大阪のシステム開発の現状と重要性
大阪のビジネスシーンにおけるシステム開発は、単なるITツール導入の域を超え、企業の経営戦略そのものを左右する重要な要素となっています。ここでは、その現状と重要性について深く掘り下げていきます。
DX推進の波と多様化するニーズ
近年、国全体で推進されているデジタルトランスフォーメーション(DX)の波は、大阪の企業にも大きな影響を与えています。特に、大阪には歴史的に製造業や卸売・小売業、そしてインバウンド需要を支えるサービス業が多く集積しており、それぞれの業界特有の課題を解決するためのシステム開発が活発化しています。
- 製造業: 生産ラインの自動化、品質管理の高度化、サプライチェーン全体の可視化などを目的とした生産管理システムやIoTプラットフォームの導入。
- 卸売・小売業: ECサイトと実店舗の連携、顧客データ分析に基づくマーケティング施策、煩雑な在庫管理を自動化するシステムの構築。
- サービス業: 予約管理システムのオンライン化、顧客管理(CRM)システムによるリピーター育成、多言語対応のWebサイト構築。
このように、各企業が抱える課題は多岐にわたり、汎用的なパッケージソフトでは対応しきれないケースが増えています。そのため、自社の業務フローに完全にフィットするオーダーメイドのシステム開発の重要性が一層高まっています。
ビジネス成長におけるシステム開発の役割
適切なシステムを導入することは、単なる業務効率化に留まらず、企業に以下のような多大なメリットをもたらします。
- 生産性の向上: 手作業で行っていた定型業務を自動化することで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できます。これにより、組織全体の生産性が向上します。
- データに基づいた意思決定: 散在していたデータを一元管理し、リアルタイムで分析・可視化することで、経営層や管理者は勘や経験だけに頼らない、客観的なデータに基づいた迅速かつ正確な意思決定が可能になります。
- 新たなビジネスモデルの創出: 蓄積されたデータを活用して新しいサービスを開発したり、顧客との接点をデジタル化してこれまでにない顧客体験を提供したりと、システムは新たなビジネスチャンスを生み出す土台となります。
- 競争力の強化: 市場の変化や顧客ニーズに迅速に対応できる柔軟なシステムを持つことで、競合他社に対する優位性を確立し、持続的な成長を実現できます。
これからの時代、システム開発は守りのIT投資ではなく、ビジネスを成長させるための攻めの戦略的投資として、ますますその重要性を増していくことは間違いありません。
システム開発会社の種類と特徴

システム開発を発注する際、パートナーとなる開発会社には様々な種類が存在します。それぞれに得意分野や特徴、費用感が異なるため、自社のプロジェクトの規模や目的、予算に最適な会社を選ぶことが成功の第一歩です。ここでは、代表的な3つの種類に分類し、その特徴を解説します。
大手システム開発会社
誰もが名前を知るような大手システム開発会社は、豊富な資金力、人材、そして数多くの大規模プロジェクトを成功させてきた実績に裏打ちされた高い信頼性が最大の魅力です。金融機関の基幹システムや官公庁のインフラ構築など、社会的な影響が大きく、絶対に失敗が許されないプロジェクトを数多く手掛けています。
最新技術の研究開発にも積極的で、AIやビッグデータ、ブロックチェーンといった先端技術を要する高度なシステム開発にも対応可能です。また、企業の課題分析といった上流工程のコンサルティングから、開発、導入、そして運用・保守までを一気通貫で任せられる総合力も強みです。
ただし、その分、費用は高額になる傾向があります。管理体制がしっかりしている反面、手続きが複雑で、仕様の微調整などにも時間と追加費用がかかるケースも少なくありません。予算が潤沢にあり、大規模かつミッションクリティカルなシステム開発を求める企業にとっては最適な選択肢となり得ます。
中小規模のシステム開発会社
大阪には、地域に根ざし、地場の中小企業のビジネスをITで支える中小規模の開発会社が数多く存在します。これらの企業の最大の強みは、顧客との距離の近さと、それによって生まれる柔軟な対応力です。
大手企業に比べて組織がスリムであるため、意思決定が迅速で、顧客の細かな要望にも小回りを利かせて対応してくれることが多いです。担当者と直接コミュニケーションを取りながら、二人三脚でプロジェクトを進めていけるため、初めてシステム開発を発注する企業にとっても安心感があります。また、大手と比較してコストパフォーマンスに優れている点も大きな魅力です。
一方で、エンジニアの数などのリソースには限りがあるため、非常に大規模なプロジェクトや、短納期での開発には対応が難しい場合があります。しかし、特定の技術領域や業界に強みを持つ会社も多く、自社のニーズと開発会社の得意分野がマッチすれば、非常に心強いパートナーとなるでしょう。
専門特化型のシステム開発会社
特定の業界(例:医療、金融、不動産、製造)や、特定の技術(例:ECサイト構築、スマホアプリ開発、AI導入支援)に特化してサービスを提供する開発会社です。
最大のメリットは、その専門性の高さにあります。例えば、医療業界特化型の会社であれば、医療法や個人情報保護に関する深い知識を持っているため、業界特有の要件をスムーズに理解し、コンプライアンスを遵守した質の高いシステムを提案してくれます。開発会社側が業務内容を深く理解しているため、発注側の説明コストが大幅に削減され、要件定義がスムーズに進むという利点もあります。
その分野における最新の技術トレンドや成功事例にも精通しているため、より効果的なソリューションの提案が期待できます。ただし、専門領域以外の開発には対応できないケースがほとんどであるため、依頼したい内容がその会社の専門分野と完全に合致しているかを見極めることが重要です。
大阪のシステム開発会社の選び方

自社に最適な開発会社を選ぶことは、プロジェクトの成否を分ける最も重要なプロセスです。ここでは、選定時に必ず確認すべき4つの重要なポイントについて解説します。
1. 必要な要件の整理
開発会社に相談する前に、まずは自社内でシステム化の目的と要件を整理しておくことが不可欠です。この準備が不十分なまま相談を始めると、話が具体的に進まなかったり、開発会社の提案を鵜呑みにするしかなくなったりしてしまいます。最低限、以下の3点は明確にしておきましょう。
- 現状の課題とシステム導入の目的:
- 「なぜシステムが必要なのか?」を突き詰めます。「手作業の入力ミスが多く、業務効率が悪い」「顧客情報がバラバラに管理されていて、営業活動に活かせていない」など、具体的な課題を洗い出します。
- その課題を解決した結果、「どうなりたいのか?」という目的を明確にします。「残業時間を月20%削減する」「顧客単価を10%向上させる」など、可能な限り定量的な目標を設定することが理想です。
- 必要な機能のリストアップ:
- 目的を達成するために、システムにどのような機能が必要かを書き出します。この時、「絶対にないと困る必須機能」と、「あると嬉しい希望機能」に分けて優先順位をつけておくと、後の予算調整や仕様決定がスムーズになります。
- 予算と希望納期:
- おおよその予算感と、いつまでにシステムを稼働させたいかという希望納期を設定します。これが開発会社を選定する際の重要な基準となります。
これらの情報が整理された「提案依頼書(RFP)」を作成しておくと、各社に同じ条件で提案を依頼できるため、比較検討が容易になります。
2. 実績と経験の確認
開発会社の能力を判断する上で、過去の実績と経験は最も客観的な指標となります。企業のウェブサイトで公開されている開発実績や導入事例を必ず確認しましょう。その際、以下の点に注目してください。
- 同業界・同規模の実績: 自社と同じ業界や、同じくらいの企業規模のプロジェクトを手掛けた経験があるかは非常に重要です。業界特有の商習慣や業務フローへの理解が期待でき、話がスムーズに進みます。
- 類似システムの開発実績: 自社が開発したいシステムと似たようなシステムの開発実績があれば、その会社は関連する技術やノウハウを既に保有している可能性が高く、プロジェクトの成功確率が高まります。
- 技術スタックの確認: どのようなプログラミング言語やフレームワーク、クラウドサービス(AWS, Azure, GCPなど)を得意としているかを確認します。自社が求めるシステムの要件と、開発会社の技術力がマッチしているかを見極めましょう。
- 顧客の声や評判: 導入事例に掲載されている顧客の声や、第三者機関による評価、口コミなども参考にし、その会社の信頼性や顧客満足度を測ります。
3. 費用感の確認と比較
システム開発は決して安い投資ではないため、費用感の確認は慎重に行う必要があります。必ず複数の会社(できれば3社以上)から相見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。
見積書を確認する際は、総額の安さだけで判断してはいけません。以下の項目を詳細にチェックし、その金額の妥当性を評価することが重要です。
- 費用の内訳: 「要件定義」「設計」「開発」「テスト」といった各工程にどれくらいの費用(工数×単価)が計上されているか。内訳が不明瞭な「一式」表記ばかりの見積書は注意が必要です。
- 前提条件の確認: 見積もりの前提となっている機能範囲や仕様が、自社の要求と合致しているかを確認します。前提が異なれば、当然金額も変わってきます。
- 追加費用の有無: 仕様変更や機能追加が発生した場合の料金体系がどうなっているか、事前に確認しておくことがトラブル防止につながります。
- 保守・運用費用: システムリリース後の保守・運用費用が月額でいくらかかるのか、その費用にどこまでのサービスが含まれるのかも重要な比較ポイントです。
安すぎる見積もりは、品質が低かったり、後から高額な追加費用を請求されたりするリスクも潜んでいます。価格と品質、サービス内容のバランスが取れた、最もコストパフォーマンスの高い会社を選びましょう。
4. アフターサポートの充実
システムは開発して終わりではなく、リリースしてからが本当のスタートです。安定して稼働させ、ビジネスの変化に合わせて改善していくためには、開発会社のアフターサポート体制が非常に重要になります。
契約前に、以下の点について必ず確認しておきましょう。
- サポートの範囲: 障害発生時の対応(原因調査、復旧作業)はもちろん、操作方法に関する問い合わせ、データのバックアップ、セキュリティアップデート、軽微な修正などがサポート範囲に含まれているか。
- サポート体制: サポートの受付時間(平日日中のみか、24時間365日か)、連絡手段(電話、メール、チャットなど)、問題発生から対応完了までの目標時間(SLA)がどのようになっているか。
- 機能追加・改修への対応: 将来的にビジネスが拡大し、システムに機能を追加したくなった場合に、柔軟に対応してもらえるか。その際の開発体制や費用感についても確認しておくと安心です。
長期的なパートナーとして付き合える、信頼性の高いサポート体制を持つ会社を選ぶことが、システムという資産価値を最大化する上で不可欠です。
システム開発プロジェクト成功のポイント

優れた開発会社を選んだとしても、プロジェクトの進め方次第でその成果は大きく変わります。ここでは、システム開発プロジェクトを成功に導くために発注側が意識すべき3つの重要なポイントを解説します。
1. クリアなコミュニケーション
システム開発は、発注側と開発側の共同作業です。両者の間に認識の齟齬があると、手戻りが発生してスケジュールが遅延したり、完成したシステムが期待したものと全く違うものになったりするリスクがあります。これを防ぐためには、徹底してクリアなコミュニケーションを心がけることが重要です。
- 定例ミーティングの設定: プロジェクトの進捗状況、課題、次のアクションなどを共有するため、週に1回程度の定例ミーティングを設けましょう。対面に加え、Web会議ツールも有効活用します。
- 担当窓口の一本化: 自社側の責任者・担当窓口を明確に決め、開発会社とのやり取りを一本化することで、情報の混乱を防ぎます。
- コミュニケーションツールの活用: メールだけでなく、ビジネスチャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど)やプロジェクト管理ツール(Backlog, Redmineなど)を活用し、迅速かつ記録に残る形でコミュニケーションを行うことが推奨されます。
- 議事録の作成と共有: ミーティングで決定した事項や課題は、必ず議事録として文書化し、双方で確認・合意することで、「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎます。
疑問や懸念点は些細なことでも放置せず、すぐに確認・共有する姿勢が、プロジェクトを円滑に進める上で不可欠です。
2. 明確なプロジェクト管理
システム開発は、多くのタスクが複雑に絡み合う長期的なプロジェクトです。ゴールを見失わず、計画通りにプロジェクトを進めるためには、発注側もプロジェクト管理に主体的に関わる必要があります。
- WBS(作業分解構成図)とスケジュールの共有: 開発会社にプロジェクト全体のタスク(WBS)と詳細なスケジュール(ガントチャート)を作成・共有してもらいましょう。これにより、いつまでに何をすべきかが明確になり、進捗状況を客観的に把握できます。
- 進捗の可視化: プロジェクト管理ツールなどを通じて、常にプロジェクトの進捗状況が可視化されている状態を保ちます。遅延が発生しているタスクがあれば、その原因と対策を速やかに開発会社と協議します。
- 課題管理表の運用: プロジェクト中に発生した課題や問題点は、課題管理表に記録し、担当者、期限、ステータス(対応中、完了など)を明確にして管理します。これにより、課題の対応漏れを防ぎます。
- スコープ管理の徹底: プロジェクトの途中で安易に機能追加(スコープの拡大)を行うと、予算超過や納期遅延の直接的な原因となります。追加要望がある場合は、その必要性を慎重に検討し、影響範囲(費用、スケジュール)について開発会社と正式に合意した上で進めるようにしましょう。
3. 適切なリスク管理
どれだけ綿密に計画を立てても、予期せぬトラブルが発生するのがプロジェクトです。重要なのは、起こりうるリスクを事前に予測し、その対策を準備しておくことです。
プロジェクト開始前に、開発会社と共に以下のようなリスクを洗い出しましょう。
- 技術的リスク: 想定していた技術では要件を実現できない、連携する外部システムに仕様変更が発生する、など。
- スケジュールリスク: 発注側の仕様決定が遅れる、担当者が急に退職・異動する、など。
- コストリスク: 予期せぬ仕様変更が多発し、予算を大幅に超過する、など。
- 品質リスク: テストが不十分で、リリース後に重大な不具合が発覚する、など。
これらのリスクに対して、「発生した場合にどのような影響があるか」「影響を最小限に抑えるために、どのような対策を講じるか」を事前に検討し、リスク管理計画として文書化しておきます。リスクを常に監視し、発生の兆候が見られたら速やかに対策を実行する体制を整えておくことで、プロジェクトが破綻する事態を防ぎ、成功へと導くことができます。
システム開発の工程と流れ
システム開発は、一般的に「ウォーターフォールモデル」と呼ばれる、上流から下流へ水が流れるように各工程を順番に進めていく手法が基本となります。ここでは、その代表的な6つの工程について、それぞれの内容と目的を解説します。
下記の記事ではシステム開発工程を各ステップごとに解説しています。
1. 要件定義
システム開発の全工程の中で最も重要と言っても過言ではないのが、この要件定義フェーズです。ここで、システムで何を実現したいのか、どのような機能が必要なのかを発注者と開発者で詳細にすり合わせ、合意形成を行います。
要件は、大きく分けて2つに分類されます。
- 機能要件: ユーザーが直接操作する機能に関する要件。「顧客情報を登録・検索できる」「商品をカートに入れて決済できる」「日々の売上レポートを自動で作成できる」など、システムが「何をできるか」を定義します。
- 非機能要件: 機能以外の品質に関する要件。性能(レスポンス速度)、可用性(稼働率)、セキュリティ、UI/UX(使いやすさ)など、システムの「どのような品質であるべきか」を定義します。
この要件定義の内容をまとめた「要件定義書」が、以降の全工程の設計図となります。ここでの定義が曖昧だと、後工程で大規模な手戻りが発生し、プロジェクト失敗の最大の原因となるため、十分な時間をかけて慎重に進める必要があります。
2. 設計
要件定義書を基に、システムの具体的な仕様を設計していくフェーズです。設計もまた、2つのステップに分かれています。
- 基本設計(外部設計): 主にユーザーの視点から見た設計を行います。画面レイアウトや操作方法(UI/UXデザイン)、帳票のフォーマット、システムが外部とやり取りするデータの仕様などを決定します。この段階で作成される「基本設計書」は、発注者と開発者がシステムの完成イメージを共有するための重要なドキュメントです。
- 詳細設計(内部設計): 主に開発者の視点から見た、システム内部の動きを詳細に設計します。基本設計で決められた機能を、どのようなプログラムの構造(モジュール分割)で実現するのか、データベースはどのようなテーブル構成にするのか、といった技術的な仕様を決定します。「詳細設計書」は、プログラマーがコーディングを行う際の直接的な指示書となります。
3. 開発(実装・コーディング)
詳細設計書に基づき、プログラマーが実際にプログラミング言語を用いてソースコードを記述していく、いわゆる「モノ作り」の工程です。このフェーズでは、単に動くプログラムを作るだけでなく、コーディング規約を遵守し、誰が見ても分かりやすく、将来の修正や機能追加が容易な「保守性の高いコード」を書くことが求められます。
開発の進捗管理には、Gitなどのバージョン管理システムが用いられ、チームでの効率的な共同作業とソースコードの変更履歴管理が行われます。
4. テスト
開発したシステムが、設計書通りに正しく動作するか、品質に問題がないかを検証する非常に重要な工程です。テストを十分に行うことで、リリース後の不具合を未然に防ぎ、システムの信頼性を担保します。テストは、小さな単位から大きな単位へと段階的に進められます。
- 単体テスト: プログラムの最小単位である関数やモジュールが、個々に正しく動作するかを開発者自身が検証します。
- 結合テスト: 単体テストをクリアした複数のモジュールを組み合わせた際に、モジュール間の連携(データの受け渡しなど)がうまく機能するかを検証します。
- システムテスト(総合テスト): 全てのモジュールを結合し、システム全体として要件定義で定められた機能・性能・セキュリティを満たしているかを検証します。
- 受入テスト(UAT): 最終段階として、実際にシステムを利用する発注者(ユーザー)が、実際の業務の流れに沿ってシステムを操作し、業務要件を満たしているかを最終確認します。
5. リリース
全てのテストをクリアし、発注者の承認を得たシステムを、ユーザーが実際に利用できる本番環境へ展開する作業です。
リリースの際には、旧システムからのデータ移行や、ユーザーが新しいシステムをスムーズに使えるようにするための操作マニュアルの提供やトレーニングの実施も併せて行われます。リリース直後は予期せぬトラブルが発生する可能性もあるため、開発会社と連携し、迅速に対応できる監視体制を整えておくことが重要です。
6. 運用・保守
システムが本番稼働を開始した後のフェーズです。安定稼働を維持するために、サーバーの監視、定期的なデータバックアップ、OSやミドルウェアのセキュリティアップデートといった保守作業が継続的に行われます。また、ユーザーからの問い合わせ対応や、障害発生時の原因調査・復旧といった運用サポートも含まれます。
ビジネス環境の変化や法改正に対応するための機能追加や改修も、このフェーズで計画・実行されます。システムを長期的に活用していくためには、この運用・保守フェーズが極めて重要となります。
システム開発の費用相場と節約方法
システム開発の費用は、開発するシステムの種類、機能の複雑さ、規模(開発工数)によって大きく変動します。一概に「いくら」とは言えませんが、一般的な目安は以下の通りです。
- 小規模なWebサイト・ツール: 数十万円~300万円程度
- 一般的な業務システム(顧客管理、在庫管理など): 300万円~1,000万円程度
- 大規模な基幹システム・複雑なWebサービス: 1,000万円以上
大阪は開発会社の数が多く競争が激しいため、価格帯にも幅があります。適正な価格で高品質なシステムを開発するためには、見積もりの取り方と費用を抑えるポイントを理解しておくことが重要です。
見積もりの取り方
前述の通り、正確な見積もりを取得するためには、「RFP(提案依頼書)」を作成し、複数の会社に同じ条件で提案を依頼することが基本です。
RFPには、以下の項目を盛り込みましょう。
- プロジェクトの背景と目的
- 現状の業務フローと課題
- システムに求める機能要件・非機能要件
- 予算と希望納期
- 選定スケジュール
提出された見積書と提案書を比較する際は、金額だけでなく、プロジェクトの進め方、開発体制、実績、そして担当者のコミュニケーション能力などを総合的に評価し、最も信頼できるパートナーを選定することが成功の鍵となります。
費用を抑えるためのポイント
開発費用を賢く抑えるためには、いくつかの有効な方法があります。
- 要件に優先順位をつけ、MVP開発を目指す: 「あれもこれも」と機能を詰め込むと、費用は青天井に膨れ上がります。まずは「これがないとビジネスが成り立たない」という最小限の必須機能(MVP: Minimum Viable Product)に絞って開発し、スモールスタートを切ることを検討しましょう。リリース後にユーザーのフィードバックを得ながら、段階的に機能を追加していくアジャイル的なアプローチは、無駄な開発コストを削減し、投資対効果を高める上で非常に有効です。
- クラウドサービス(SaaS/PaaS)を活用する: 全ての機能をゼロから開発するのではなく、既存のクラウドサービスを積極的に活用することも有効な手段です。例えば、認証機能はAuth0、決済機能はStripeといったSaaSを利用したり、サーバー構築の手間を省けるPaaS(AWS、 GCPなど)を開発基盤として利用したりすることで、開発工数を大幅に削減できます。
- 補助金・助成金を活用する: 国や大阪府、各自治体は、中小企業のIT導入やDX推進を支援するための様々な補助金・助成金制度を用意しています。「IT導入補助金」などが代表的です。これらの制度を活用することで、システム開発費用の一部を補助してもらえる可能性があります。開発会社の中には、補助金申請のサポートに詳しい企業もあるため、相談してみるのも良いでしょう。
- オープンソースソフトウェア(OSS)を活用する: OSやデータベース、各種ライブラリなどを商用製品ではなくオープンソースで構成することで、ライセンス費用を削減できます。多くの開発会社はOSSの活用に長けているため、積極的に提案を求めましょう。
これらのポイントを意識することで、予算内で最大限の効果を発揮するシステム開発を実現することが可能になります。
まとめ
本記事では、大阪でシステム開発を検討する企業様に向けて、その全体像を網羅的に解説しました。
大阪の活気あるビジネス環境で企業が成長を続けるためには、自社の課題を解決し、競争力を高めるための戦略的なシステム導入が不可欠です。システム開発は複雑で専門性の高い領域ですが、成功の鍵は非常にシンプルです。それは、「自社の目的を明確にし、その目的達成を共に目指せる信頼できる開発パートナーを見つけること」に尽きます。
大阪には、大手から中小、専門特化型まで、多種多様な強みを持つ開発会社が存在します。今回ご紹介した「会社の選び方」や「プロジェクト成功のポイント」を参考に、ぜひ複数の会社とコンタクトを取り、自社に最適なパートナーを見つけてください。
システム開発は、企業の未来を形作る重要な投資です。この記事が、その第一歩を踏み出すための確かな道しるべとなれば幸いです。
「カスタメディア」は、新規事業としてシェアリングエコノミー、マッチングサービス、サブスク、SaaSなどのデジタルプラットフォームビジネスを立ち上げる方々に向けた、サイト構築システムの「型」の集合体です。これまで800件以上のサービスを提供して培ったノウハウを凝縮しており、低価格・短納期でのサイト構築が可能です。
多産多死という新規事業の特性を踏まえ、低コストで迅速に無駄のない施策を多数試行し、反応に応じて小刻みにビジネスをピボットをさせて改善していくことで、他にはない革新的なアプローチで新規事業立ち上げ支援を行っています。