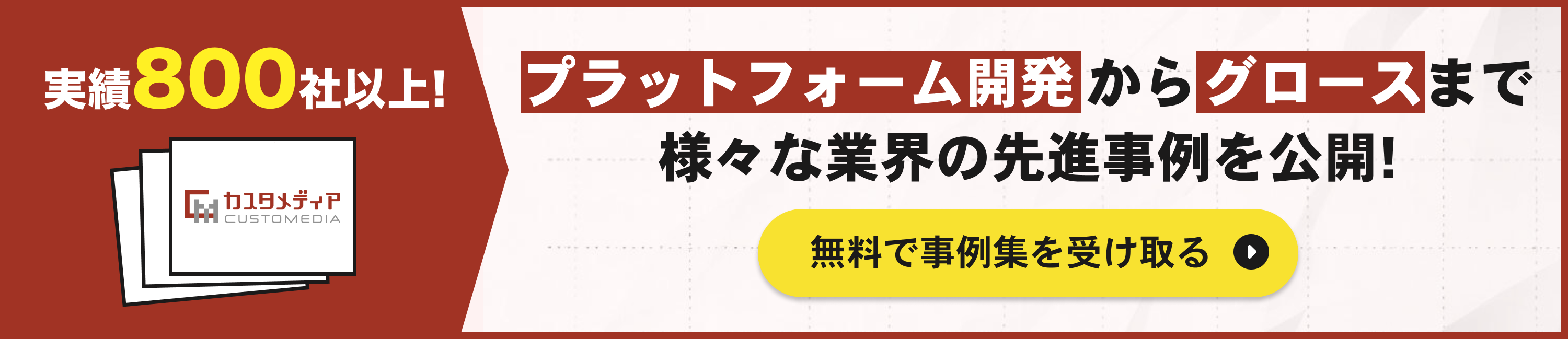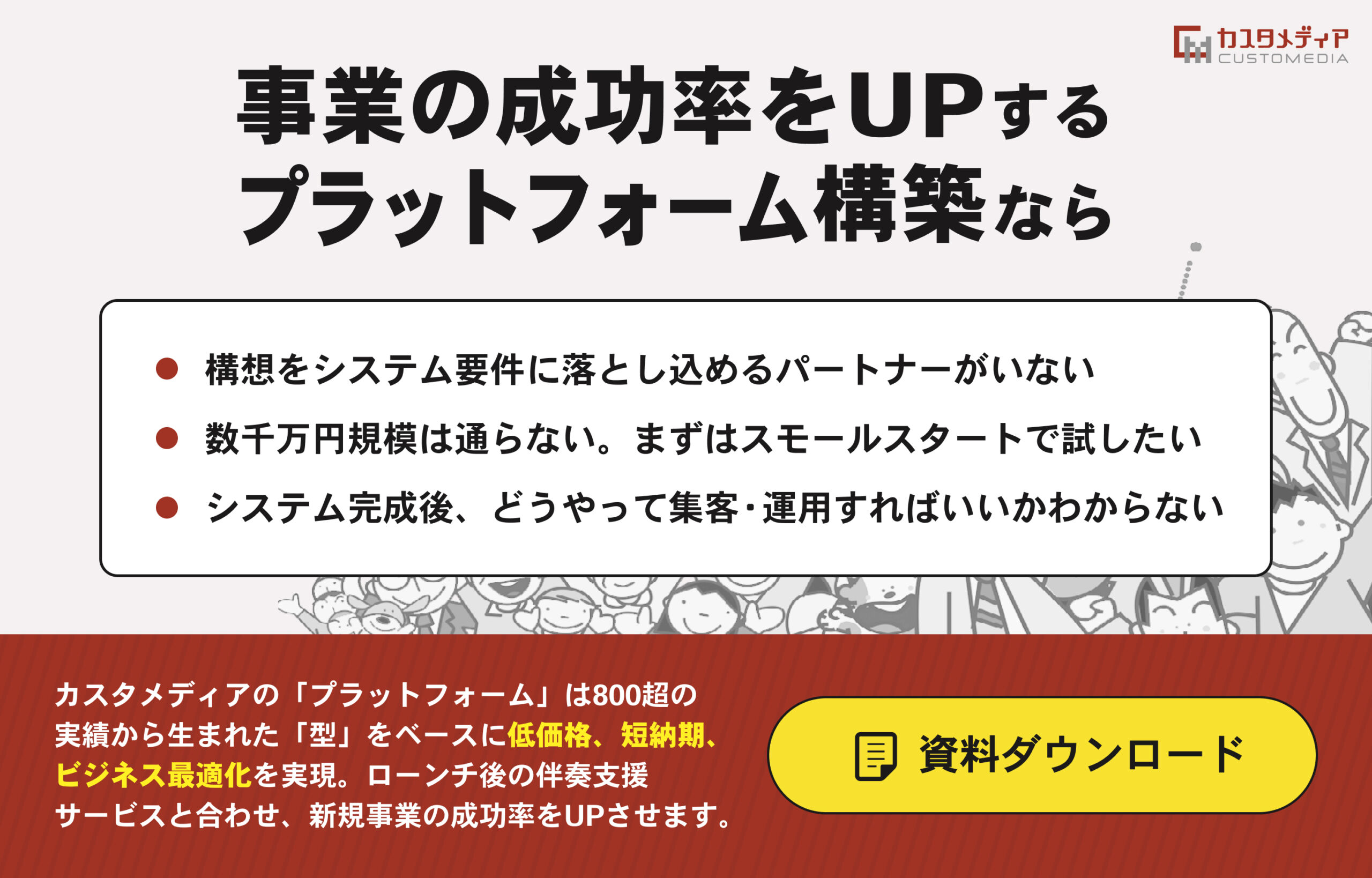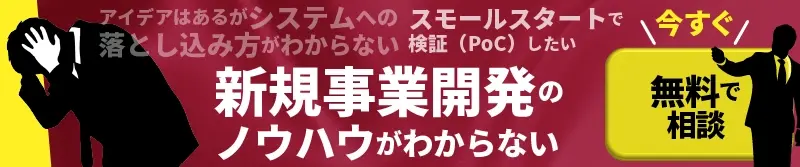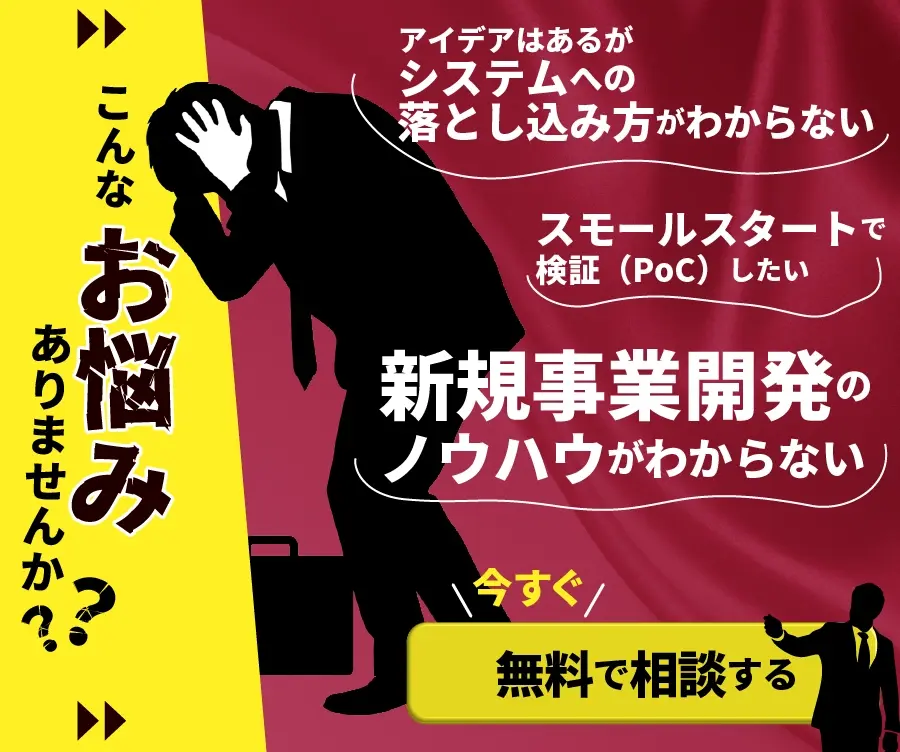マーケティングBLOG

【2026年最新版】シェアリングスペースの種類・料金・使い方を徹底解説!
導入実績800サイト以上!!
「カスタメディア」の事例ダウンロードは
こちら
働き方の多様化が加速する2026年、場所を所有せず賢く利用する「シェアリングスペース」は不可欠なインフラとなりました。
現在は事務作業のみならず、副業の店舗運営や企業のサテライト拠点など活用範囲が劇的に拡大。「自宅では集中できない」「低リスクで起業したい」といったニーズに、高品質な環境を低コストで提供します。本記事では、最新の種類や料金相場、失敗しない選び方を徹底解説します。
目次
シェアリングスペースとは何?
シェアリングスペースとは、オフィスや会議室などの施設を、複数の利用者が「必要な時だけ共同で利用する」形態のスペースです。
「所有」するのではなく、高品質な環境を「必要な分だけ賢くシェアする」新しいワークスタイル・ライフスタイルの選択肢です。
3つの大きな特徴
- 柔軟な利用スタイル 時間単位や月単位など、用途に合わせて必要な分だけレンタルできます。
- 圧倒的なコスト削減 自社でオフィスを構える際の敷金・礼金や、デスク・Wi-Fiなどの設備投資を大幅に抑えられます。
- ビジネスチャンスの創出 異業種の人々が集まるため、単なる作業場を超えた「交流」や「新しいアイデア」が生まれる拠点となります。
主要なシェアリングスペースの種類
2026年現在、シェアリングスペースは「場所を借りる」だけでなく、「専門設備をシェアする」「隙間時間を活用する」という多様な進化を遂げています。ここでは、目的別に4つのカテゴリに分けてご紹介します。
ビジネス・ワーク系
コワーキングスペース
フリーアドレス形式でデスクやWi-Fiを利用できる空間です。2026年には「Business-Airport」のようなホスピタリティ重視の拠点や、地方の空き家を再生した地域密着型など、選択肢が非常に広がっています。
また、全国展開している「いいオフィス」では、地域密着型の店舗から大型拠点まで多彩な選択肢があり、仕事場所を自由に選びたい人に好評です。Wi-Fiや電源、会議室など基本設備が整っており、都度利用・月額利用のどちらにも対応しています。
- 特徴:オープンデスク、Wi-Fi、電源、会議室が完備された共同環境
- 活用シーン:フリーランサーはもちろん、外資系企業やスタートアップの利用。出張中の作業、ビジネス交流などがあります。
貸会議室
貸会議室は、社外での商談やセミナー、採用面接などに活用されるビジネス向けスペースです。大手の「TKP貸会議室」は、全国の駅近に多数の拠点を展開しており、必要な時間だけ予約できる便利さが魅力です。
たとえば、東京・丸の内にあるTKP会議室では、プロジェクターやホワイトボードなどの備品も充実しており、スムーズなプレゼンテーションが可能です。アクセスの良さや空間の清潔感は、クライアントとの信頼構築にもつながります。
- 特徴:モニター、ホワイトボード、高品質なWeb会議用設備が揃う個室環境
- 活用シーン:重要な商談、採用面接、社内セミナー、オフサイトミーティングなど
個室ワークポッド(スマートポッド)
駅ナカや商業施設に設置された、1人用防音個室。2026年現在は「STATION BOOTH」が主要駅のインフラとして定着しており、IoT連携によりスマホ一つで即座に解錠・利用が可能です。 移動の合間に、周囲の視線を気にせず「テレキューブ」のようなセキュアな空間でWeb会議ができるため、ハイブリッドワーク時代の必須ツールとなっています。
- 特徴:遮音・換気完備の極小個室。スマホアプリで予約から決済まで完結するシステ
厶 - 活用シーン:移動中の急なWeb会議への参加、機密性の高い電話連絡、短時間の集中
作業など
専門スキル・店舗運営系
シェアキッチン
飲食店営業許可取得済みの厨房をシェアします。初期費用を抑えて「食」のビジネスをスタートできます。 たとえば「8K(ハチケー)」のような菓子製造・カフェ営業に特化した施設や、デリバリー専門の「KitchenBASE」を活用することで、リスクを抑えた開業が可能です。
- 特徴:プロ仕様のコンロやオーブンを完備。保健所の許可基準を満たしており、即営業が可能
- 活用シーン:ゴーストレストラン、ネット販売用の菓子製造、料理教室、1日限定カフ
エの開催など
シェアサロン
美容師や整体師が施術を行うための専門スペース。「GO TODAY SHAiRE SALON」は2026年4月に札幌新店をオープンするなど全国へ拡大しており、独立した個人の活動拠点として定着しています。 「ビューティシェア」などのプラットフォームを使えば、空き時間に自分だけのサロンを持つことも容易です。
- 特徴:シャンプー台や施術ベッド、鏡などが物理的に整った美容・癒やしの専用空間
- 活用シーン:フリーランス美容師の顧客施術、週末限定の副業サロン営業、独立に向けたプレ営業など
シェアリングジム
パーソナルトレーナーの指導や、個人の集中トレーニングに特化した個室ジム空間です。 「ジムカリ」や「ミライトジム」といったサービスにより、24時間いつでも本格的な機材を独占して利用できる環境が整っています。
- 特徴:パワーラック等の本格機材が揃う完全個室。周囲の視線を気にせずトレーニングが可能
- 活用シーン:フリーのトレーナーの指導場所、個人による本格的なワークアウト、動画撮影を伴うトレーニングなど
イベント・レジャー・宿泊系
パーティースペース・スタジオ
懇親会から動画収録まで、多目的に使える空間。「スペースマーケット」では古民家や屋上テラスなど多彩な空間を選べ、「インスタベース」でも趣味の集まりや練習場所に最適なスペースが豊富に見つかります。
一方、エンタメ性を重視したい場合は、「パセラリゾーツ」の貸切スペースが人気です。カラオケや食事、映像演出が揃っており、少人数の集まりから大規模なパーティーまで対応可能です。
- 特徴:キッチン、大型モニター、撮影用照明、防音設備などが揃う多目的空間
- 活用シーン:女子会や誕生日会、YouTube・SNS用の動画収録、ブランドのポップアップイベントなど
民泊・ホテル一体型スペース
マンションの一室やホテルの空き時間を活用。2026年は「Airbnb」がショートトリップやイベント連動型旅行のトレンドを牽引しており、「STAY JAPAN」のような地域密着型のユニークな宿泊体験も人気です。
- 特徴:生活設備のある宿泊空間。最近はホテルのラウンジをワーク開放するモデルが
急増 - 活用シーン:暮らすような長期出張、ワーケーション、イベント参加時の滞在、チーム
合宿など
アセット・インフラ系
シェア駐車場
自宅や店舗の空き駐車場を予約利用。2026年は「akippa(あきっぱ)」や「特P」がEV充電設備付きスポットとの連携を強化しており、移動の不安を解消する社会インフラとなっています。
- 特徴:個人宅の空きスペースなどを予約制で提供。現地での満車トラブルを回避でき
る - 活用シーン:イベント会場周辺の駐車場確保、安価な月極・時間貸しの代替など
マイクロモビリティポート(シェアサイクル等)
ビルの軒下等のデッドスペースを活用した駐輪拠点。「LUUP(ループ)」や「HELLO CYCLING」のポートが街中に浸透し、24時間レンタル・返却が可能です。
- 特徴:スマホアプリで解錠。駅から目的地への「ラストワンマイル」を埋めるインフラ
- 活用シーン:駅からオフィスまでの移動、営業先が点在する際の効率的な移動手段、観光地での周遊など
シェア倉庫・物置き
ビルの地下室や住宅の空きスペースを荷物預かりとして活用。「モノオク」なら近所の物置きを格安で借りられ、「サマリーポケット」を使えばアプリ一つで荷物の管理から配送まで完結します。
- 特徴:専用アプリで在庫管理が可能。自宅のクローゼット代わりに使える物理的スペース
- 活用シーン:季節物の保管、ECショップの在庫置き場、引越し前の一時預かりなど
シェアリングスペースのメリットとデメリット
シェアリングスペースの活用は、単なる「経費削減」を超え、ビジネスの機動力や創造性を高める戦略的な選択肢となっています。一方で、2026年現在においては、デジタルセキュリティや作業環境の管理といった新たな課題への配慮も求められます。
メリット
圧倒的なコストパフォーマンスと柔軟性
敷金や礼金、什器の購入費用といった初期投資をゼロに抑えられます。月額制や15分単位のドロップインなど、プロジェクトの規模やライフサイクルに合わせて「必要な時に必要な分だけ」利用できるため、固定費の変動費化が可能です。
新たなビジネスチャンスを生むネットワーク
異業種や異なる専門スキルを持つ人々が物理的に同じ空間を共有することで、カフェや自宅では得られない「偶発的な出会い」が生まれます。2026年現在は、利用者同士のマッチングを支援するコミュニティマネージャーや専用アプリを備えた施設も増えており、共同プロジェクトの立ち上げや情報交換の質が飛躍的に向上しています。
生産性を高める高品質なインフラ
超高速Wi-Fi、Web会議専用ブース、エルゴノミクスチェア、さらには高機能な複合機やコーヒーバリスタなど、個人では維持が難しい「プロ仕様の環境」を安価に利用できます。
デメリット
セキュリティと情報保護の課題
不特定多数が利用するため、PC画面の覗き見(ショルダーハック)や、Web会議中の会話漏洩といったリスクが伴います。2026年現在は、「個室ワークポッド」や「プライバシーフィルター」の活用が必須の対策となっています。
環境による集中力のバラつき
周囲の話し声や移動の音が気になる場合があります。自身の作業スタイル(静寂が必要か、適度な雑音があった方が捗るか)に合わせて、静音エリアの有無やブースの遮音性を事前に確認する必要があります。
ルールとマナーの制約
共用スペースである以上、電話の禁止区域やキッチンの利用方法など、施設独自のルールを守る必要があります。また、2026年現在は「Web会議での話し声の大きさ」に関するマナーが特に重視されており、周囲への配慮が求められます。
シェアリングスペースの料金相場と選び方
シェアリングスペースを賢く使うには、「料金相場の把握・目的に合った選び方・お得な利用法」の3つがポイントです。料金は地域や設備によって大きく変わるため、まずは相場を知り、自分のニーズに合うスペースを選びましょう。ここでは、地域ごとの料金の目安、選び方のコツ、そしてお得に使うための工夫について解説します。
地域別の料金目安(東京・大阪・地方)
エリアによって料金は大きく異なります。
東京では、レンタルオフィスや会議室の料金は1時間あたり3,000円〜10,000円程度。特に都心のビジネス街では、平日昼間の需要が高いため、料金が高めに設定されています。
大阪は東京よりやや安く、2,000円〜8,000円程度が一般的です。中心部でも、東京ほどの価格にはなりにくく、利用しやすい傾向があります。
地方都市では、1,000円〜5,000円程度で利用できる場所が多く、料金的には最もリーズナブルです。最近では、個人オーナーや地域に根ざした運営によるユニークなスペースも増えており、選択肢も広がっています。
選ぶ際のポイント(立地・用途・設備・運営元の信頼性など)
選ぶときは、「アクセス」「用途」「設備」「運営元の信頼性」をチェックしましょう。
まず重要なのは立地です。駅からの距離や通勤経路との相性は、利用頻度に直結します。遠すぎると結局使わなくなるケースもあるため、アクセスは要確認です。
次に、自分の目的に合った使い方ができるかどうかも大切です。たとえば、集中して作業したいなら静かな個室タイプ。打ち合わせをするなら会議室タイプ。撮影や配信が目的なら照明や背景の整ったスペースが必要です。
設備面では、Wi-Fiや電源、プロジェクター、ホワイトボードなど、必要なものが揃っているかどうかを事前に確認しましょう。
そして、運営元が信頼できるかも重要です。レビューや口コミを確認することで、実際の使い勝手やトラブルの有無などが把握できます。
お得に使うためのポイント(定額制・時間帯利用など)
定額制・オフピークの活用・会員特典がカギです。
頻繁に使うなら、月額制の定額プランを検討しましょう。定額で一定時間使えるため、コストの見通しが立てやすく、結果的に割安になることが多いです。
また、平日昼間や早朝などの空いている時間帯は、割引料金が設定されていることもあります。混雑を避けつつコストも抑えられるため、時間に融通が利く人にはおすすめです。
おすすめのシェアリングスペース活用事例
シェアリングスペースは、働く場所の自由度を広げるだけでなく、コミュニティや学び、発信の場としても活用が広がっています。ここでは、代表的な4つの活用シーンを、実際の事例とともに紹介します。
スタートアップやフリーランスの拠点
スタートアップやフリーランスにとって、最小限のコストでプロフェッショナルな拠点を構える手段として、シェアリングスペースは非常に有効です。
法人登記ができるオフィス型のスペースや、来客対応が可能な会議室付きの施設なども多く、事業のフェーズに応じて柔軟に選べる点が魅力です。オフィスを一から借りるよりも圧倒的にハードルが低く、仲間づくりやネットワーキングの機会も豊富です。

事例:WeWork(全国)
世界的に展開するコワーキングブランド「WeWork」では、多くのスタートアップやベンチャー企業が拠点として活用しています。たとえば、ITスタートアップの「Gracia株式会社」は、WeWork渋谷スクランブルスクエアに拠点を構え、スピーディな事業立ち上げを実現しました。
法人登記、会議室の利用、イベント参加など、多様な機能がワンパッケージで利用できる点が評価されています
副業やオンライン講師の作業場
副業やオンラインでの仕事をする人にとって、集中できる“第二の作業場”としてのシェアリングスペースは欠かせない存在です。
特にオンライン講師や動画編集者、Web会議の多いビジネスパーソンにとっては、個室・高速Wi-Fi・静かな環境といった条件が整ったスペースが重宝されています。

事例:basis point(東京・横浜・名古屋など)
「basis point」は、都市部を中心に展開する時間貸しのコワーキングスペース。個室ブースが充実しており、周囲の雑音を気にせず、ZoomやGoogle Meetなどのオンライン授業・会議に集中できます。
副業でオンライン講師をしているBさんは「自宅よりも落ち着いて授業ができ、信頼感も上がった」と語っています。
イベント・撮影・勉強会の開催
貸しスペースは、ビジネスセミナーや交流イベント、動画撮影など、目的に応じて多様な使い方ができます。
特に近年では、YouTubeやInstagramの発信拠点として、撮影機材や照明の揃ったスペースの需要も高まっています。

事例:SPOT
スペースシェアリングサービス「スペースマーケット」では、料理イベント、スタジオ撮影、勉強会などに適したスペースが多数登録されています。
例えば、渋谷の白ホリスタジオは、ポートレート撮影やVlog撮影の定番スポット。撮影背景・ライティングが整っており、プロアマ問わず人気です。
地域コミュニティやママ会などの場
シェアリングスペースは、地域の人が集う「交流の場」としても活用されています。
子育て世代やシニア層など、さまざまな人々が日常的に集まり、イベントやおしゃべりを通してコミュニティが育まれる空間です。

事例:まちのね浜甲子園(兵庫県西宮市)
「まちのね浜甲子園」は、空き家を活用した地域密着型スペース。平日にはママ会や子育てサロン、週末にはフリーマーケットやワークショップが開催されています。
地域住民が主体となって運営し、「誰もが安心して集まれる場所」として親しまれています。
シェアリングスペースの今後の可能性
シェアリングスペースは今、フリーランスの作業場という枠を超え、企業の経営戦略や地域再生の切り札へと進化しています。現在、物理的なオフィスの制約から解放された「新しい働き方のインフラ」として、どのような未来を描いているのか。3つの主要トレンドから解説します。
企業の「分散型オフィス」戦略のコアへ
オフィスコストの最適化と社員のエンゲージメント向上を両立させるため、シェアリングスペースを「戦略的サテライト拠点」として導入する企業が一般化しました。
単なる一時的な利用ではなく、プロジェクトごとに最適な場所を選んだり、地方でのワーケーション拠点として活用したりすることで、生産性を最大化する「ABW(Activity Based Working)」の基盤となっています。
空き家活用・地域活性化の「ハブ」としての役割
全国的な課題である空き家・空き店舗の再活用策として、シェアリングスペースが重要な役割を担っています。地方の遊休資産をワークスペースや交流拠点へ再生することで、地域外からの人の流れ(関係人口)を創出し、経済の活性化に貢献しています。
事例:長野県塩尻市「スナバ(sunya-ba)」
空き家だった米穀店をリノベーションし、行政・企業・住民が共創する拠点。会議やワークショップの場としてだけでなく、地元の農産物販売やアート展示など、地域の文化とビジネスが交差する「地域資源を活かす場」として持続可能なまちづくりを支えています。
先端テクノロジー(Web3・メタバース)との融合
物理的な空間とデジタルテクノロジーが高度に融合する「ハイブリッド・シェアリング」が加速しています。
Web3・DAOによる共創運営
ブロックチェーンを活用し、利用者自身がスペースの運営方針や設備投資の意思決定に参加するDAO(分散型自律組織)型の運営モデルが登場。利用者が「客」ではなく「運営パートナー」となることで、より熱量の高いコミュニティが形成されています。
今後のトレンド予測
今後のシェアリングスペースのトレンドとして、まず挙げられるのはテクノロジーの進化です。特に、 IoT(モノのインターネット)を活用したスマートオフィス機能が、利用者にとってより快適な環境を提供します。たとえば、予約システムや空調管理などが自動化されることで、効率的にスペースを利用できます。
次に、地域密着型のビジネスが増加するでしょう。都市部だけでなく、地方都市でもシェアリングスペースが登場し、地域のニーズに応じたサービスが展開されることが予想されます。これにより、地方経済の活性化や地方での新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。
最後に、健康やウェルネスを重視したスペースの増加も考えられます。リモートワークによる孤立感を解消するため、共用スペースにコミュニティの要素を持たせ、心身の健康をサポートする環境作りが進むでしょう。このように、シェアリングスペースは将来的にも多様な進化を遂げていくと期待されています。
まとめ
シェアリングスペースの利用は、ビジネスパーソンにとって非常に有用な選択肢となります。リモートワークが普及する現代において、自由な働き方を可能にするこのサービスは、特にフリーランサーや中小企業の経営者に最適です。
また、これからのシェアリングスペースは、単に「場所をシェアする」だけではありません。テクノロジーを駆使し、地域社会とつながり、多様な人々が共創する「新しい価値を生み出すためのプラットフォーム」へとその役割を広げていくでしょう。
シェアリングスペースのサービスにおいてサイト構築を検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!